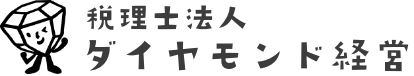相続贈与・事業承継SERVICE 03
税務申告で納税額に差が出てくるのが相続税申告です。相続財産の評価はグレーゾーンが多く税理士が変われば評価額が変わり税額が大きく変わります。一般的な相続対策の手順を以下に示しますが、具体的な対策はそれぞれの家庭の状況や財産内容によって変わります。
相続贈与
- 1.遺言書の作成・家族信託の活用
遺言書や家族信託を用意することで、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、自分の意志を反映できます。
家族信託で財産管理や運用を円滑に行うことができます。 - 2.生前贈与の活用
生前贈与をすることで、相続税の負担を減らすことが可能です。贈与税の改正が行われましたが、年間110万円の非課税枠を利用することは確実に相続税対策になります。
自社株式の評価額を下げて、後継者に生前贈与する対策も有効です。 - 3.相続税対策
不動産評価額を下げるための各種特例や控除の活用、相続税法以外の建築基準法や条例を適用することにより評価額を下げることができます。
財産評価通達よりも不動産の現況や各種法律が優先します。 - 4.不動産の有効活用
不動産を法人名義にすることにより、相続税評価額を下げることができます。納税資金が足りない場合には、不動産等を売却することも視野に入れましょう。
不良資産(貸宅地等)の売却(整理)は早めに進めることが大切です。 - 5.生命保険の活用
生命保険は非課税枠があるため、課税対象の財産を減らしつつ一定の納税資金を準備する手段として大変有効です。
利益繰延型ではなく掛け捨て型の生命保険をおすすめします。
重要なのは、各家庭の事情や価値観に応じてカスタマイズした対策を講じることです。
事業承継
事業承継は一歩誤ると最悪の事態に突入します。早めの対策を講じましょう
- ●現役社長の相続が突然発生すると、信用不安(社内・取引先・銀行)が起きる
- ●現役社長が会社借入金の連帯保証人になっている場合には要注意
- ●自社株対策の方向性を検証する(分割・合併・株式移転・株式交換)
- ●後継者に経営者としての経験値を早めに積ませる
- ●現社長との伴走期間とブレインの育成期間が必要
- ●後継者がいない場合にはM&Aも視野に入れる
一番大事なことは、後継者との意見の調整です。じっくり話し合いましょう。